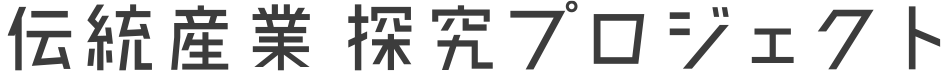
国内で古くから使用されてきた天然塗料「漆」について、伝統技術を守りながらも時代のニーズに対応した新たな挑戦を学びつつ、
産地の現状や自然と人間の関係性(生態系)を探究します。
2日目は右京区京北地域の合併記念の森(工藝の森)に赴きました。1日目に引き続き、講師に堤浅吉漆店 堤卓也氏をお迎えし、漆をはじめ樹木や植生などを教えていただきながら、漆の生育の難しさや「工藝の森」での取り組みについて話を伺いました。
その後、ファブビレッジ京北で丹波漆の漆掻き職人である山内耕祐氏から、15年かけて植樹した丹波漆や漆を育てる環境の変遷をお聞きし、実際に漆掻きされた漆の木を見ながら、ここまでの体験で出てきた「疑問」を書き出し、伝統産業と自然の関係について学びを深めました。







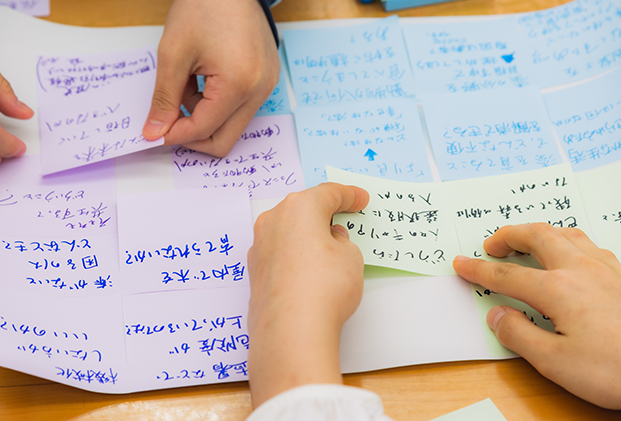







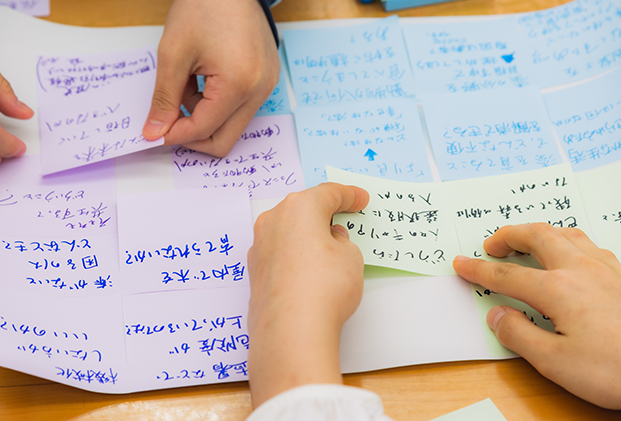


合併記念の森で植樹された漆の木を見たり、漆掻き職人の方の話を伺う中で、漆の木は10年以上育ててようやく樹液が採れるうえ、採取量も非常に限られていると知りました。そんな状況の中で、漆を生活の中に取り入れ、漆器というかたちで長く使っていたという点に、人と自然の信頼関係があるのではないかと考えました。
特に、作る側も使う側も、自然の都合に合わせて暮らしを組み立てていた、という点が印象的でした。現代の「すぐに手に入る」「すぐに使える」という感覚とは対照的で、自然と共にある生活リズムが見えてきます。こうした文化が成り立つ背景には、自然には限りがある、という理解が必要だと考えました。
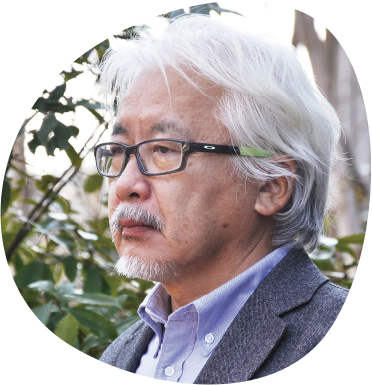
人と自然をつなぐ「工藝」をまさに実感できた1日だったのではないだろうか。暑い中で森を歩き、手間ひまかけて育てた漆の木を見て何を感じただろうか。
「もうけること」「便利さ」そして「豊かな生活」とは。知れば知るほど、学べば学ぶほど、学生みんなの問いが深まったと思う。
答えは出なくてもいい。それでも、問い続けてほしいと願う。
1日目は京都市下京区にある堤淺吉漆店に赴きました。午前中は、工場で漆が生成される過程や漆独特の道具の説明を受けたり、漆塗りのサーフボードやスケートボードなど漆の魅力を伝えるために取り組まれていることを見学も交えながらお話を伺いました。午後は、拭きうるし体験を通して実際に漆に触れた後、講師の堤卓也さん、スワローさん、阿部コーディネーターとともに対話を重ね、学びを深めました。


















今回は京都市内の漆店にて、漆の特徴や現在抱えている課題、お店の方々が漆を広めるために行なっている取り組みなどについてお話を伺いました。
私は、今回の体験で人間が「自然のありがたみ」を忘れてしまっていることが問題だと感じました。自然のありがたみを忘れたために、環境を守ることに関心がない。自然と密接に関わる伝統産業にも関心がない。未来に自然を残すどころか、今にも失われるのではないかと考えました。時代に合わせて柔軟に変化し、興味の入り口を横に広げるだけでなく、実際に目で見て、触れてもらう体験を行うことが古くから続く伝統産業の存続に必要だと私は感じました。そして、林業も含め、農業や水産業といった、「自然の恵みを頂く」1次産業が最も大切にされるべき。今回の活動は改めてそう考えるきっかけになりました。次回のフィールドワークや、京北のものづくりに関するお話も、とても楽しみです!
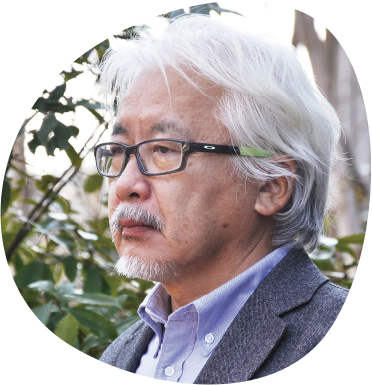
京都の路地裏にひっそりと佇む「堤淺吉漆店」。
漆を「材料」と言いつつも、そこに深い愛を感じられる堤さんの話を学生の皆はどう受け止めただろうか。
縦糸が伝統。変わることで変えてはいけないことをつなぐ。横糸が世界とのつながり。
縦糸と横糸が織りなす伝統産業、伝統文化を直に感じ、そして、直面している課題についてもこの探究プログラムを通じて考えていってほしい。